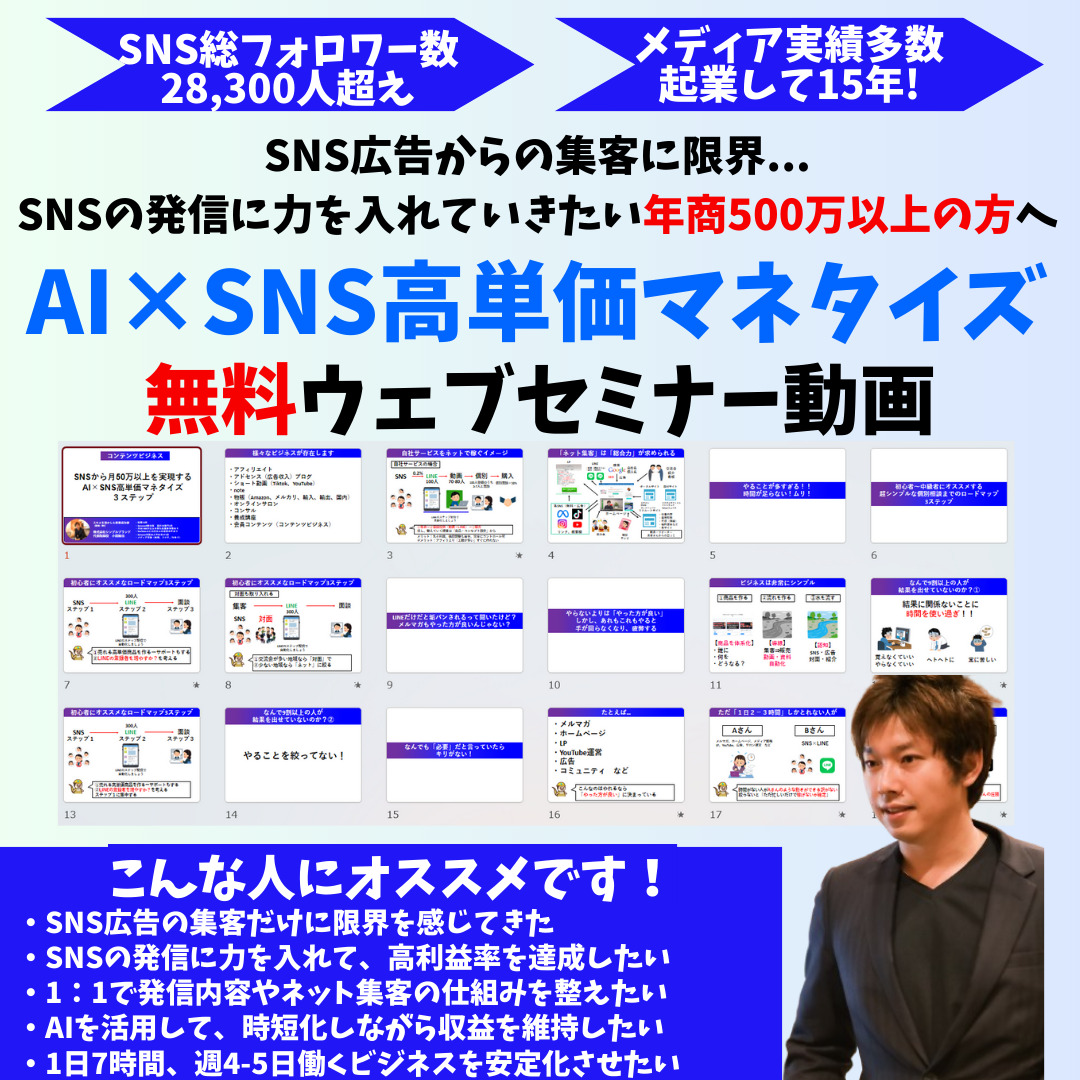なぜ今「ウェルビーイング」が注目されているのか
近年、ビジネスの現場でも頻繁に耳にするようになった「ウェルビーイング(Well-being)」という言葉。
これは、単に健康であるという状態を超えて、「身体的・精神的・社会的に良好な状態」を意味します。
特に企業においては、従業員のウェルビーイングが生産性や離職率、組織の活性化に深く関係していることが明らかになってきました。
こうした背景から、「ウェルビーイング講演」や「ウェルビーイング研修」が注目を集めています。
現在、国際的な目標として、SDGs(Sustainable Development Goals)=持続可能な開発目標が掲げられていますが、2030年以降からは、SWGs(Sustainable Well-being Goals)=みんなで持続可能なウェルビーイングの状態状態を目指す)へ移行するように言われています。詳しくはこちら(ベネッセウェルビーイングLabより)
本記事では、ウェルビーイング講演・研修の具体的な内容や導入のメリット、成功事例までをわかりやすく解説します。
ウェルビーイングとは?その本質的な意味を理解する
WHOでは「健康」とは、単に病気でないというだけでなく、「身体的・精神的・社会的に完全に良好な状態であること」
つまり、身体の健康だけでなく、心の安定や人間関係の良好さ、自己実現の感覚まで含まれます。
ウェルビーイング(Well-being)は、「Well(良い)」+「being(なっている)」つまり、「良い状態になっている」ことを指しています。
この表現は、非常に曖昧では?と感じられるかもしれませんが、「良い状態」というのは「人それぞれの主観」であるということをぜひ理解して欲しいのです。
どんなことをやってることが「幸せ」を感じるの?
どんなことをやってるのが「楽しいの」?
これらは全て本人が感じる「主観」ですよね。
特に「周りの目を気にしながらも、どこかびくびくしながら生きている日本人」にとっては、「思い切って楽しむこと」や「幸せだと感じられるマインド」が重要だと言えます。
特に現代社会では、ストレス社会とも言われる中、心身の健康を維持しながら、自分らしく働き、生きることが強く求められているので、そのお手伝いができるべく、講演や研修を行っています。
ウェルビーイング講演とは何か?
ウェルビーイング講演とは、専門家や実務家が登壇し、「幸せに働くための考え方」や「ストレスマネジメント」「マインドフルネス」などをテーマに、ウェルビーイングの概念や実践方法をわかりやすく解説するセッションです。
主に以下のようなテーマが扱われます。
①心の健康と職場環境の関係
②エンゲージメント向上とウェルビーイング
➂ワークライフバランスの最適化
④自己肯定感を高める思考法
⑤組織と個人のウェルビーイング実践事例
参加者にとって気づきと実践のヒントを得られる機会となり、企業としても「従業員第一」の姿勢を示すことができます。
ウェルビーイング研修の内容と構成
ウェルビーイング研修は、講演に比べてより実践的・体験的なプログラムが中心となります。
単なる知識提供ではなく、実際に自分の行動や考え方を変えるきっかけを提供するのが特徴です。
主な研修内容には以下のようなものがあります。
ストレスマネジメントの実践ワーク
価値観の明確化ワークショップ
マインドフルネス瞑想や呼吸法の体験
ポジティブ心理学に基づいた対話セッション
チームビルディングを通じた関係構築演習
受講後は「前向きに働く力」や「自分らしさを活かす視点」が得られるため、離職率の低下や生産性の向上につながります。
ウェルビーイングの講演内容の詳細
 小田じゅん
小田じゅんウェルビーイングの講演に関する内容の一部を紹介します!
ストレスマネジメントの実践ワーク
ストレスの仕組みや自分のストレス傾向を知ることから始まり、具体的な対処法(呼吸法、セルフトークの変え方、短時間でリセットする方法など)を体験型で学びます。実際の業務にすぐに活かせる内容となっており、日常のストレス軽減と心の安定に大きな効果があります。
価値観の明確化ワークショップ
自分の中にある「大切にしたい価値観」を掘り下げるワークを行います。価値観が不明確だと、仕事に対してのモチベーションが揺らぎやすくなります。この研修では、自己理解を深め、自分らしい意思決定やキャリア設計の軸を見つけることができます。
マインドフルネス瞑想や呼吸法の体験
「今、この瞬間」に意識を向けるマインドフルネスの基本を学び、実際に呼吸法や簡単な瞑想を体験します。心を静める技術として世界中の企業で導入されており、集中力の向上や感情のセルフコントロールに効果があります。初めての人でも取り組みやすい内容です。
ポジティブ心理学に基づいた対話セッション
感情や強みにフォーカスした「ポジティブ心理学」をベースにした研修です。ペアワークやグループディスカッションを通じて、自己の強みやポジティブな感情を引き出し、周囲との関係性も深めていきます。仕事への前向きな姿勢を育てるのに最適です。
チームビルディングを通じた関係構築演習
同僚との関係性を見直し、信頼関係を強めることを目的とした演習型研修です。共通の目標に向かって協働するアクティビティや、フィードバックのトレーニングを通じて、チーム内のコミュニケーション力を高め、心理的安全性のある職場づくりを支援します。
なぜ企業にとってウェルビーイングが必要なのか?
 小田じゅん
小田じゅん従業員のウェルビーイングを高めることは、単なる福利厚生の充実にとどまりません。経営戦略そのものにも直結する重要な要素です。
生産性と創造性の向上
心身の状態が良好であれば、集中力や創造力が高まり、結果的に仕事のパフォーマンスも向上します。
離職率の低下
職場に安心感と自己成長の実感があると、離職率が大幅に下がります。
組織文化の改善
ウェルビーイングの考え方が浸透することで、心理的安全性の高い職場風土が生まれます。
導入のステップ:ウェルビーイング講演・研修を実施するには
 小田じゅん
小田じゅんウェルビーイング講演・研修の導入は、以下のステップで進めるのが一般的です。
①課題の明確化
従業員アンケートや面談を通じて、現場の課題を把握します。
②講師やプログラムの選定
組織の課題や目的に合った専門家を選定します。
➂講演・研修の実施
目的やテーマに応じて内容をカスタマイズし、実施します。
④フィードバックと効果測定
受講後アンケートや定量的な指標(生産性・満足度)で効果を分析します。
講師選びのポイントとは?
講師の選定は非常に重要ですので、選び方のポイントを5つご紹介します。
ウェルビーイングに関する講演や研修は、講師の質によって参加者の満足度や行動変容に大きく差が出ます。
① 専門知識と実績のバランスがある
心理学、組織開発、ヘルスケアなど、ウェルビーイングに関連する専門知識を持ちつつ、企業や団体への導入実績が豊富な講師が理想です。また、知識だけでなく、実務での応用経験があるかを確認しておきましょう。
② 参加者を巻き込むファシリテーション力がある
ウェルビーイング研修は「対話型・体験型」であることが多く、講師の話術や進行の巧みさが成功のカギを握ります。受け身にならず、自然に参加者が自己開示したくなるような雰囲気を作れるかが重要です。
③ 自社の課題や文化への理解度が高い
講師が業界や企業規模、課題感に対する理解を持っているかは非常に大切です。事前の打ち合わせでヒアリングをしっかり行い、会社の状況に合わせた内容にカスタマイズしてくれる講師を選びましょう。
④ 実践的な提案やアフターフォローがあるか
講演や研修後に、「どう実務に落とし込むか」「継続的にウェルビーイングを推進する方法」についての具体的な提案や資料提供がある講師は信頼できます。アフターフォローの体制も確認しましょう。
⑤ 人柄・共感力がある
ウェルビーイングは「心」に関わるテーマです。講師自身があたたかく誠実な人柄であり、参加者に寄り添う姿勢があるかどうかはとても大切です。動画や過去の登壇の様子を見て判断するのもおすすめです。
ちなみに、弊社シンプルブランドの小田は、多くの芸能人、タレント、オリンピック選手などが登録している「日刊スポーツ派遣講演ナビ」にも登録されている1人になります。


社員一人ひとりの変化が、組織の未来を変える
ウェルビーイング講演・研修は、単なる「イベント」ではありません。
それは、社員一人ひとりの意識を変え、職場全体を前向きなエネルギーで包む「文化改革」の一歩です。
日々の忙しさの中で、自分自身の心身に向き合う時間を持つこと。
それが、持続可能な働き方と企業の成長の鍵となるのです。
ウェルビーイングの一貫として「健康脳のつくり方」というコンテンツを提供しています。
集中力が続かない、モチベが湧かないなど、こういった情報はすべて「脳」が判断しているため、この脳を健康の状態にしておかないと、いくら良い情報・セミナーを学んだとしても、行動まで落とし込めないんです。
健康脳のつくり方に興味のある方はこちらの記事を読まれてください。
まとめ
ウェルビーイング講演・研修は、従業員の心身の健康や職場の人間関係、働きがいの向上を目的とした、これからの時代に欠かせない人材育成施策です。
単なる福利厚生にとどまらず、企業の生産性向上、離職率の低下、チームの信頼関係強化といった経営的な成果にも直結します。
ストレスマネジメント、マインドフルネス、価値観の明確化など、研修テーマごとの明確な目的と手法を理解し、実践的な講演・研修を選ぶことが重要です。
また、講師選定の際には、専門性と人間性、企業課題への理解力を兼ね備えた人物を選ぶことで、より効果的な学びと変化を引き出すことができます。社員のウェルビーイング向上は、企業の持続的成長の鍵であり、今こそ積極的に取り組むべき経営戦略です。
もしウェルビーイングの講演を希望される方は、下記のボタンよりお申込みください。
-13.jpg)