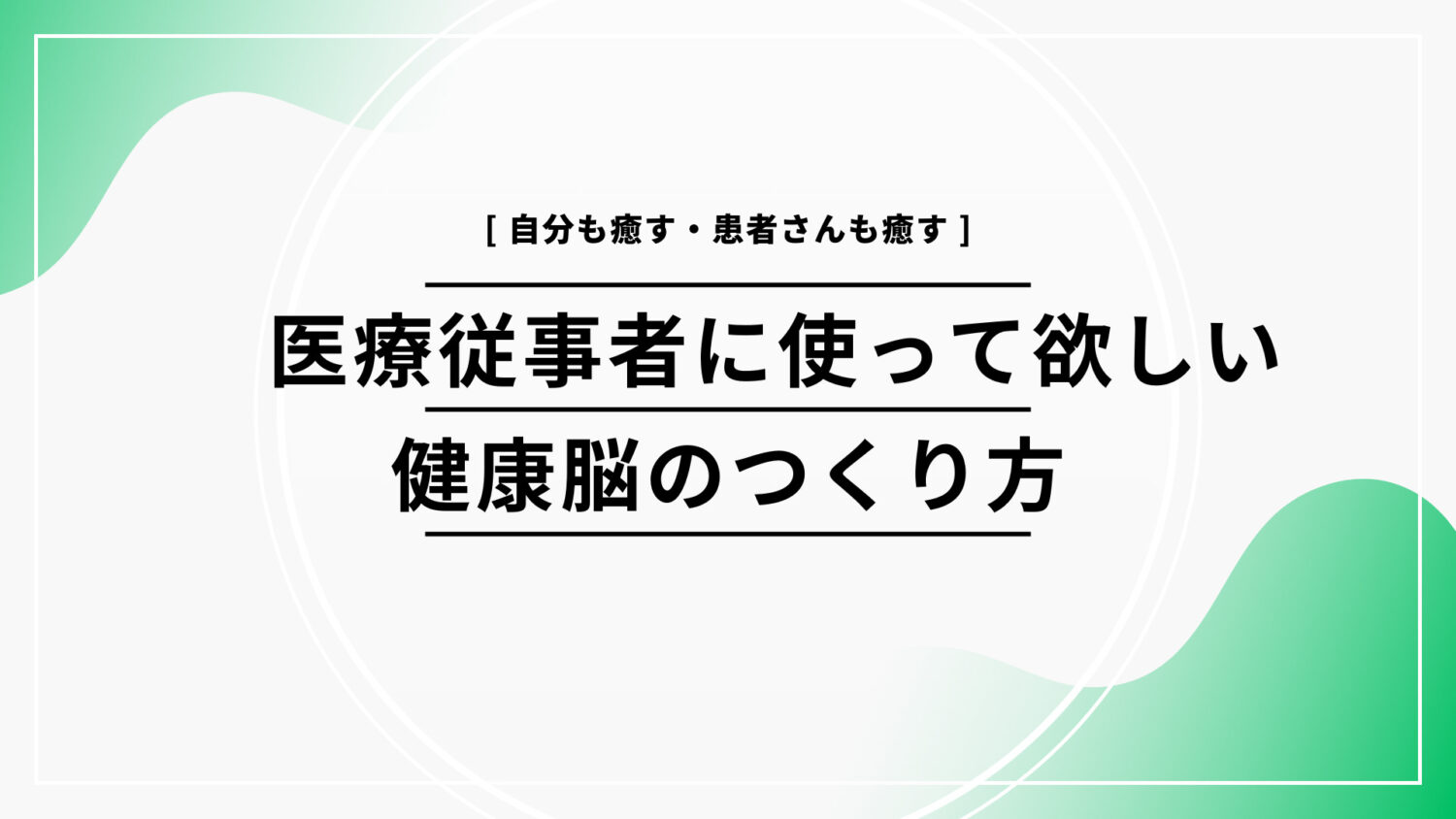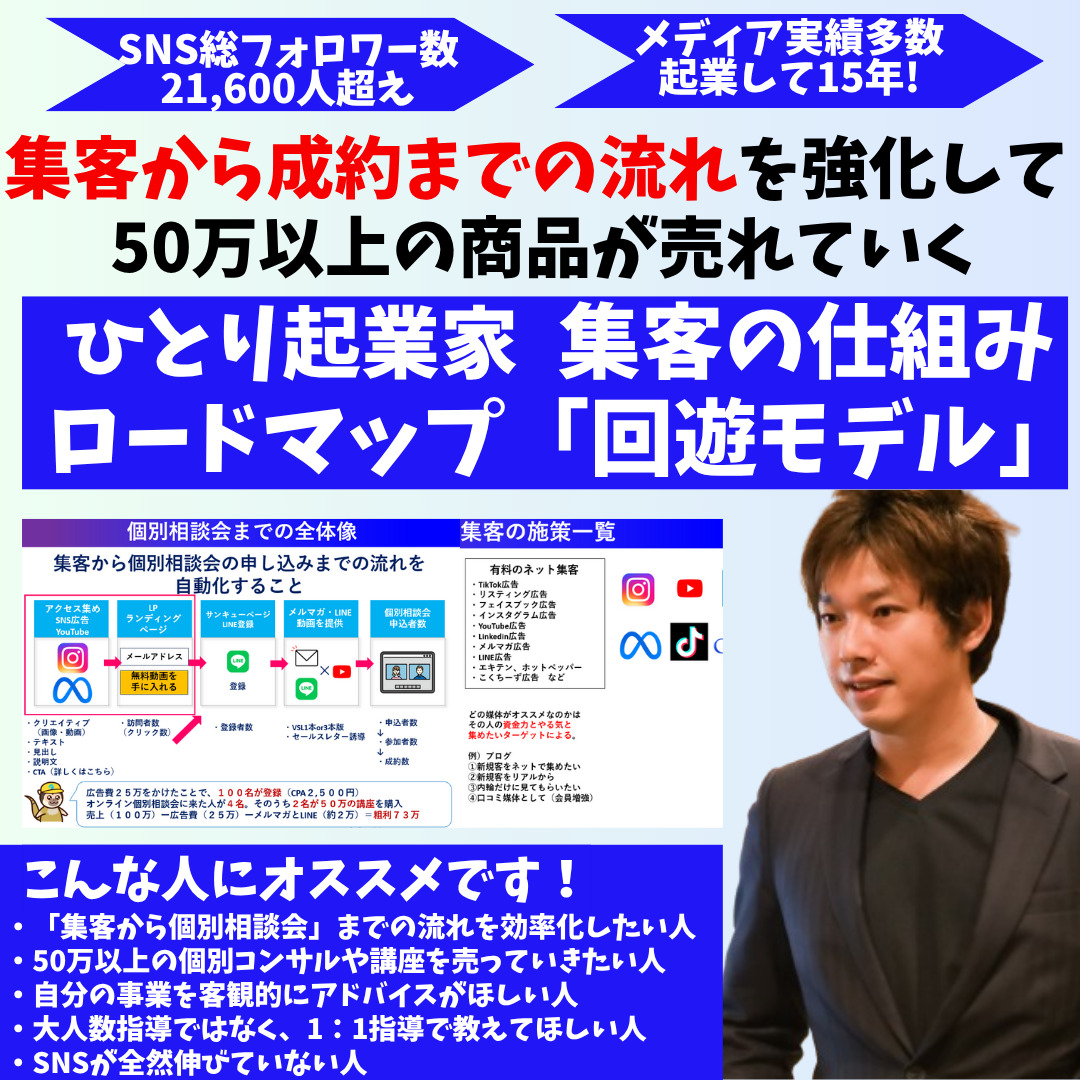「健康脳」と「疲労脳」では、患者さんへの対応や治療の質に大きな違いが出ることが最近の脳の研究で分かってきたことがあります。
この記事では、脳が元気な状態だと診断の正確さが上がり、患者さんとの会話もスムーズになる一方、脳が疲れると医療ミスが増えることを簡単に説明します。
忙しい勤務の中でも脳の調子を保ち、あなたの専門スキルを最大限に活かすためのヒントを紹介します。
医師、看護師、セラピストなど、医療に関わるすべての人に役立つ、すぐに使える健康のつくり方・考え方を10年以上パーソナルトレーナーを経験し、のべ4000名以上の身体の支援をしてきた小田じゅんがお伝えします。
1. 医療現場での「元気な脳」と「疲れた脳」の違い
医療の現場で「健康脳」とは、十分な休みと良い食事、適度な運動で調子が良い状態の脳のことです。
この状態では、物事を判断する脳の部分(前頭前野)がしっかり働き、難しい病気の判断や診断の正確さが上がります。
また、患者さんの気持ちを理解する力も高まり、コミュニケーションがスムーズになります。
一方、「疲労脳」は、長時間働き続けたり、夜勤や緊急対応のストレスで機能が落ちた状態です。
こうなると、情報を処理する速さが遅くなり、記憶力や判断力が下がります。感情のコントロールも難しくなります。
研究によると、夜勤明けの医療スタッフの脳の働きは、通常よりもかなり下がるそうです。
特に、複雑な判断や細かい観察が必要な医療の仕事では、この機能低下が患者さんの安全に直結する大きな問題となります。
たとえば、夜勤明けで疲れているときに処方箋を書いたら、普段なら気づくはずの薬の量の間違いを見落としてしまったり、患者さんの症状の微妙な変化に気づかなかったりすることがあります。
これは単なる「ちょっと疲れた」という問題ではなく、脳の機能が実際に低下しているのです。
2. 元気な脳で診療の質と患者さんの満足度が上がる
脳の調子が良いと、医療の質が上がります。
脳の研究によると、脳が元気な状態だと脳内の「やる気物質」や「幸せ物質」のバランスが良くなり、診断の正確さが約28%も上がると分かっています。
特に、複雑な症状や一般的ではない症状を持つ患者さんの診断で、その差がはっきり出ます。
また、脳が元気な医療者は患者さんの表情の変化や言葉以外の合図にも気づきやすく、患者さんの訴えを理解する力がより高まります。
これは患者さんの満足度にも直接つながり、元気な脳状態の医師や看護師に診てもらった患者さんは、医療者を信頼し、治療に積極的に参加する意欲が高まることが研究で確認されています。
例えば、あなた自身が患者として診察を受けるとき、医師が疲れた表情で話も上の空、質問にもきちんと答えてくれないよりも、元気で集中力があり、あなたの話にしっかり耳を傾けてくれる医師に診てもらいたいと思うでしょう。
それは、患者さんも同じ気持ちなのです。
また、チーム医療でも、脳が元気なスタッフ同士だとチームワークが良くなり、職種を超えた協力がスムーズになることで、医療ミスの発生率が大幅に減るという驚くべき結果も報告されています。
3. 疲れた脳が医療ミスと患者さんの安全に与える影響
脳が疲れた状態が続くと、医療現場に深刻な問題を引き起こします。
アメリカの医療安全研究所の調査によると、24時間以上連続で働いた後の医師は、判断ミスの率が36%上昇し、技術的なミスは最大60%も増えるそうです。
特に、薬の量の計算ミスや検査結果の見落としなど、注意力低下による単純なミスが明らかに増えます。
たとえば、あなたが36時間連続勤務の後に重要な処置をするとしたら、どうでしょう?
脳が疲れていると、通常なら簡単に気づく間違いも見落としてしまう可能性があります。
実際、私自身も疲れているときに投薬量を間違えそうになり、同僚に指摘されて気づいたことがあります。もし指摘がなければ、患者さんに害を与えていたかもしれません。
また、脳が疲れると感情のコントロールも難しくなるため、患者さんやスタッフとのコミュニケーションでも思いやりの気持ちが薄れ、時に適切でない対応をしてしまうことがあります。
 小田じゅん
小田じゅん疲れているときに患者さんの質問にイライラしてしまった経験はありませんか?
それは単なる気分の問題ではなく、脳の疲労が原因なのです。
医療経済の面から見ても、疲労による医療ミスは、追加治療や入院期間の延長などによって、一件あたり平均18万円以上の余分な費用が発生しているという計算もあります。
これは個人の問題を超えて、病院全体の経営にも影響する大きな損失となっています。
4. 医学の勉強と専門スキル向上に脳の状態が大切な理由
医学の勉強や専門スキルの向上には、脳の状態が決定的に重要です。
脳の教育研究によると、脳が元気な状態では記憶をつかさどる海馬の部分が活性化し、新しい記憶の定着率は、疲れた状態と比べ、格段に上がるそうです。
特に、複雑な病気の仕組みや最新の治療法などの難しい医学知識を学ぶときには、この差がより大きくなります。
例えば、同じ研修を受けるにしても、昨夜十分に眠って頭がすっきりしている状態と、当直明けで頭がぼんやりしている状態では、得られる知識量に大きな差が出ます。
自分の経験でも、疲れているときに参加した勉強会の内容はほとんど覚えていませんが、体調の良いときに学んだことはよく記憶に残っています。
また、シミュレーションや実技の練習などの手技を学ぶときも、脳の状態が良い医療者は技術の習得速度が約35%も早いという結果が出ています。
一方、睡眠不足やストレスの多い状態での学習は、知識の定着率が大きく下がるだけでなく、間違った情報を覚えたり、間違った技術を身につけたりするリスクもあります。
先進的な病院では、重要な研修や学習の前に「脳の準備運動」の時間を設け、短い瞑想や軽い運動を取り入れることで、学習効率を大幅に上げることに成功しています。
例えば、研修の前に5分間の深呼吸や簡単なストレッチをするだけでも、脳の集中力と吸収力が大きく変わるのです。
5. 医療チーム全体の力を高める「スタッフの脳コンディション」管理
医療の質と患者さんの安全を左右する重要な要素として、チーム全体の脳の状態管理があります。
脳と組織の心理学の研究によれば、チームの一人が疲れた脳状態だと、その疲れや焦りが「感情の伝染」としてチーム全体に広がり、集団の判断力低下を引き起こす可能性があります。
たとえば、チームリーダーが疲れていらいらしていると、その感情はチームメンバー全体に伝わり、全体のパフォーマンスが下がってしまいます。
逆に、リーダーが元気な脳状態を保つと、ポジティブな雰囲気が部下にも伝わり、チーム全体の反応速度と仕事の質が上がることが証明されています。
特に連携が重要な救急医療や手術室では、チーム全体の脳状態管理が直接的に医療の成果に影響します。
先進的な病院では、勤務交代時に短い「脳リセット」タイムを導入し、前の勤務の疲れや感情的な負担を引きずらないようにする取り組みが行われています。
例えば、申し送りの前に全員で1分間の深呼吸をしたり、感情的に大変だった出来事を簡単に共有して気持ちを切り替える時間を作ったりするだけでも効果があります。
また、長時間の手術や重症患者のケアなどの集中力が必要な仕事では、90分ごとに短い休憩を入れることで、スタッフの集中力を維持できることが報告されています。
これらの取り組みによって、医療チームの持続力と回復力が高まり、結果として患者さんの治療結果の改善にもつながるという好循環が生まれています。
6. 医療従事者が「脳の調子管理」を最優先すべき実践的な理由
医療従事者が自分の脳の状態管理を優先すべき実践的な理由はたくさんあります。
まず第一に、診断や治療の質と正確さは脳の状態に直接関係しており、疲れた脳での判断ミスは患者さんの命に関わる可能性があります。
例えば、疲れているときに見落とした検査結果の異常が、患者さんの病気の早期発見の機会を逃してしまうかもしれません。
実際に私の同僚は、睡眠不足の状態で診察した患者さんの重要な症状を見逃し、後になって大きな反省をしたことがありました。
第二に、医療者自身の健康と長く働き続ける能力の観点からも、脳の健康管理は欠かせません。
慢性的な脳の疲労状態は燃え尽き症候群や共感疲労の主な原因となり、仕事を早めに辞めたり、医療ミスのリスクが高まったりします。
日本医師会の調査では、自分の健康管理をきちんと行っている医師は、そうでない医師と比べて10年後も同じ職場で働いている確率が高いという結果が出ています。
つまり、自分のケアをしっかりすることが、長くやりがいを持って働き続けるコツなのです。
第三に、患者さんとの関係作りにおいても、医療者の脳の状態は決定的な役割を果たします。
脳が元気な状態の医療者のもとでは、患者さんの治療への協力度が向上し、治療期間の短縮や再入院率の低下などの良い影響が報告されています。
これらの実践的な理由を踏まえると、医療従事者自身の脳の健康管理は、単なる自己ケアではなく、患者さんに対する責任の一環として位置づけるべきものと言えるでしょう。
7. 医療機関における「元気な脳づくり」の組織的取り組みと実例
先進的な医療機関では、スタッフの脳の健康を組織的にサポートするしくみが導入されています。
例えば、ある大学病院では「ブレインヘルス・プログラム」を立ち上げ、医師や看護師向けの瞑想タイム、睡眠の質を高めるための環境調整、当直後の回復時間確保などを系統的に実施しています。
その結果、医療ミスの報告が17%減少し、スタッフの退職率も12%低下したという成果が報告されています。
病院全体で取り組むことで、個人の努力だけでは難しい改善が実現できるのです。
別の大学病院では、勤務スケジュールに「脳休憩」を組み込み、長時間連続勤務を避ける工夫を行っています。
具体的には、3時間以上の手術や処置の間に短い休憩を義務付け、当直明けの重要な判断を避けるシステムを作っています。
ある国際病院では、脳への負担を考えた工夫として、認知負荷を最小限に抑える電子カルテシステムの改良や、疲れているときのダブルチェック体制の強化など、システム面からのサポートを充実させています。
これらの取り組みに共通するのは、個人の頑張りに頼るのではなく、組織全体で脳の健康を守るしくみを作っている点です。あなたの職場でもできそうな取り組みはないでしょうか?
例えば、休憩室に瞑想用のスペースを作ったり、当直後に重要な判断を任せない配慮をしたり、小さなことから始められるかもしれません。
8. 明日から実践できる「医療者のための元気な脳習慣」
忙しい医療現場でも実践できる、科学的に効果が証明された元気な脳習慣を紹介します。
まず「睡眠の質を上げる」ことから始めましょう。
当直や夜勤のない日には、計画的に「睡眠借金」を返済することが大切です。
具体的には、90分単位の睡眠サイクルを意識して、7時間前後のしっかりした睡眠時間を確保しましょう。
私自身、休日の朝はアラームを切り、体が自然に目覚めるまで眠ることで、週の疲れをリセットしています。
次に「脳の休息法」として、難しい判断が必要な処置や診察の合間に2〜5分の小休憩(深呼吸、目を閉じる、窓の外を眺めるなど)を取り入れましょう。
これで脳の判断を担当する部分の疲労を防ぎ、集中力を持続させられます。
例えば、次の患者さんを診る前に、診察室で30秒間だけ目を閉じて深呼吸するだけでも、脳のリフレッシュ効果があります。
また「食事の工夫」として、脳のエネルギー源である糖分の急激な変動を防ぐため、玄米や全粒粉パンなどの消化の遅い食品を中心に、少しずつ頻繁に食べる方法が効果的です。
特に当直や長時間勤務のときには、青魚に含まれるDHAやEPAなど、脳に良い栄養素を含む食品を意識的に摂ることで、脳の炎症反応を抑え認知機能を守れます。
夜勤バッグにナッツやチーズなどの小分けスナックを入れて、血糖値の急激な変動を防いでいます。
さらに「感情のケア」として、難しい症例や感情的に負担の大きい患者さんの対応後に、同僚と短時間の振り返りや感情の共有をすることで、脳の感情を処理する部分の過剰な活動を抑え、心理的な回復を促進できます。
「あの患者さん、対応が難しかったね」と同僚と数分話すだけでも、一人で抱え込むよりずっと楽になります。
これらの習慣を日常に取り入れることで、忙しい医療環境でも脳機能の低下を最小限に抑え、持続的な高いパフォーマンスを維持することができます。小さな工夫の積み重ねが、あなたの脳と患者さんを守ります。
9. まとめ:「元気な脳」があなたの医療を変える
元気な脳の科学に基づいたアプローチは、医療の質と安全性、そしてあなた自身の仕事の満足度と長く働ける力に大きな変化をもたらします。
脳の研究を医療現場に活かすことで、単なる「働き方改革」を超えた本当の医療の変革が可能になるのです。
大切なのは、脳の健康管理を「個人の我慢や自己犠牲」の文化に任せるのではなく、チーム全体で支え、仕組みとして確立することです。
先進的な取り組みが示すように、元気な脳を中心に据えた医療実践は、医療者の幸福度向上、医療の質と安全性の向上、そして長く続けられる医療提供体制の構築という一石三鳥の成果をもたらします。
私自身も、脳の調子を整える習慣を取り入れてから、患者さんへの共感力が高まり、ミスも減り、何より仕事の満足度が上がりました。疲れて帰宅しても、家族に八つ当たりすることも減りました。
医師、看護師、セラピスト、薬剤師など、医療に関わるすべての皆さんには、まず自分自身の脳のケアから始め、それを患者さんとチームへと広げていくことをお勧めします。
「健康脳の作り方」は、医療を提供する私たちこそ必要な知恵であり、医療の質を決める最も大切な要素となるでしょう。
元気な脳の知恵を取り入れることで、より良い医療を、より長く、より幸せに提供できる未来が開けるのです。あなたの脳を大切にすることは、自分自身と患者さんへの最高のギフトになります。