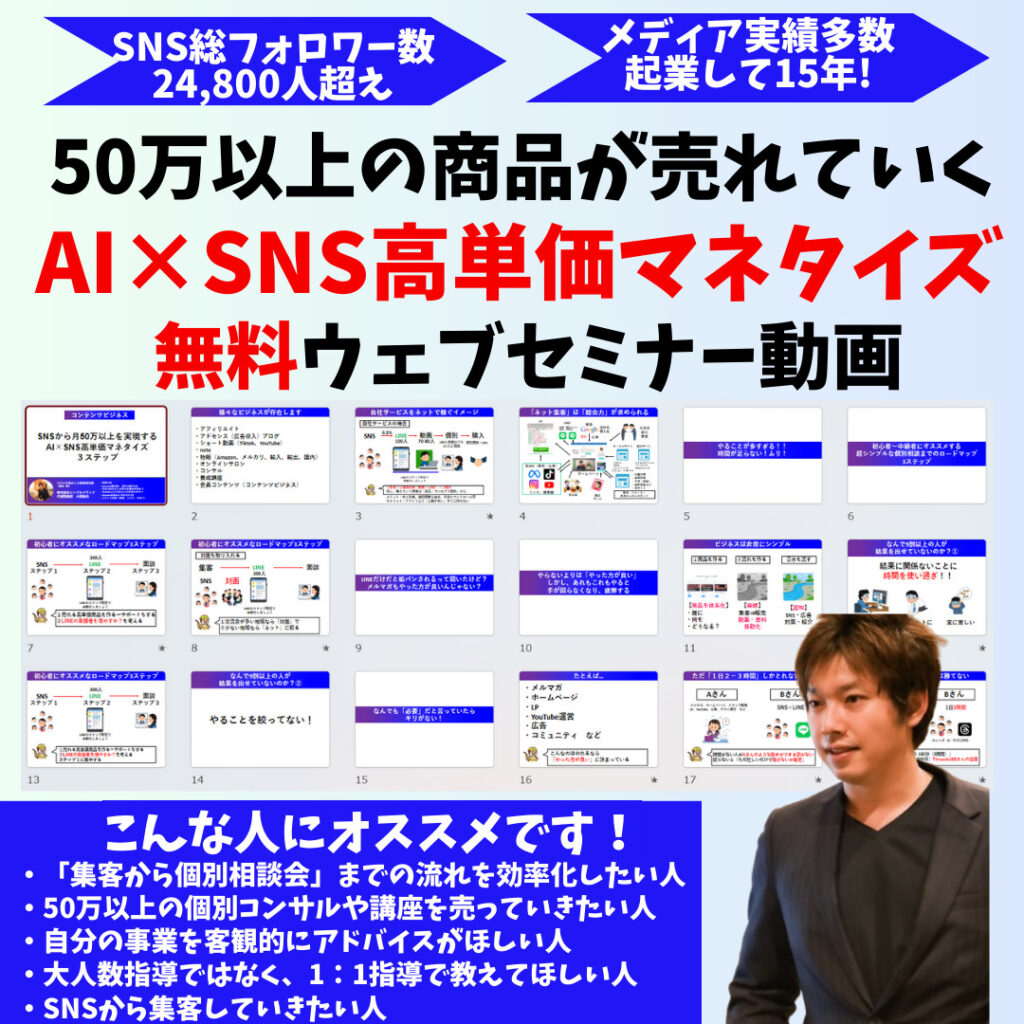今回は少し刺激的なテーマ「伴奏型支援のコンサルがキライな理由」についてお話しします。
ビジネスや自己成長の場面でよく耳にする最近流行りの“伴奏型支援”という言葉。
聞こえはやさしく、なんとなく安心感もあります。
しかし、このスタイルのコンサルには強い違和感を感じています。
なぜかというと、それは“依存”と“甘え”を生み出しやすい構造だからです。
「先生と生徒の関係」が崩れた瞬間に起こること
本来、教える人と学ぶ人には一定の距離感が必要だと考えます。
これは「上下関係」という話ではなく、「役割の明確さ」の話です。
先生は方向性を示し、導く存在。一方、生徒はその導きを自分の力に変える存在。
しかし、伴奏型のコンサルが「対等です」「一緒に歩みます」となった瞬間、この役割分担がぼやけ始めます。
するとどうなるか。生徒が甘え始めます。
・やっていないことを他人のせいにする(他責)
・「どうせ先生が手を差し伸べてくれる」と思い込む
・厳しいフィードバックを受け取れなくなる
こうして、生徒さんの中には“自己成長を止めるシステム”が完成してしまうのです。
甘えた先に「言葉は届かない」
甘えた状態になると、人は耳が閉じてしまいます。
どんなに的確なアドバイスをしても、どんなに有益なフィードバックを与えても、相手には届きません。
それどころか、「わかってくれない」「冷たい」などと逆ギレされることさえあります。
めちゃくちゃスゴイ人の近くにいる人だと、講演し終わった後は
「今日の○○先生のトークのキレはいつも以上によかったor悪かった」みたいな評論家のような発言をする場合があります。
これは非常に危険な状況です。
なぜなら、本人は自分が“素直に聞く耳を持っていない状態”にすら気づけないからです。
つまり、成長の最大のチャンスを、本人が自ら(無自覚)で捨てていることになっているということです。
伴奏依存で「口だけの自責人間」が爆誕する
「自責思考が大事」と言う人は多いです。
しかし、実際には「自責っぽいことを口では言うけど、行動が伴っていない人」が多く見受けられます。
伴奏型支援のコンサルに慣れてしまうと、何でも相談できる安心感と引き換えに、行動責任が曖昧になります。
「これってどうすればいいですか?」
「どう思いますか?」
「やっぱり難しいですよね…」
このように、“行動する前に相談”する癖がついてしまいます。
まるで許可をもらわないと前に進めない子どものような状態です。
相談し続けるだけなのに、行動した気になる。
相談し続けるだけなのに、「自分ってちゃんと相手の話を聞いている!私って素直♪エライ♪」
頭がお花畑過ぎて、ヤバすぎます。。。
とてもじゃないですが、自営業には向いていないと思わざるを得ないような思考です。
でも、それはそれで当然で自営業が全員向いている訳ではありません。組織人だからこそ、力を発揮する人はたくさんいます。
最近もフリーランスに憧れを持って独立したものの、会社員に出戻りする人が増えているようなので、その辺りも詳しく知りたい人は下記のページをご覧ください。
【出戻り増加中】「自由な働き方」は幻想だった?フリーランスから会社員へ回帰する人が増えている背景
伴奏型支援コンサルのデメリット
実際に「伴奏型」のデメリットがちらほらと出てることに気付いていますか?
かんたんに言えば「他責・依存型な人」が増えるということです。
言い方は悪いとは思いますが、副業に対して、結構舐めている印象な人が増えているなぁという印象です。
「何が舐めているか」というと
・自分の体調によってやれたらやる
・1日1時間ちょっとやれば、月20-30万なんかすぐでしょ(本業いくらもらってるんだよw)
・すぐ自信がない、しんどいと言う
・ちょっと上手くいかない程度で、心がズタボロになる豆腐メンタルなど
こういう姿勢の人です。
SNSやネットのユーザーは、そんな姿勢の人、瞬間的に察しますよ。

「え、この人に金出すの?あり得ない!」
「存在しなかったか」のようにスルーされてて「来ない」んですよ。
そういう人がビジネスの世界で結果を出すのは、難しいからこそ、僕は常に「姿勢」を説いているわけです。
僕から見ても「この人は結果が出そうだぞ~~!」って人は、愚直に積み重ねているし、言い訳を言わず、やってますからね。
自分で言うのもなんですが、客観的に見ても、そこそこやっている組ですが、それでも「あー俺って所詮まだこの程度なんだな」って感じですからね。
副業に取り組んで「疲れる」なんて当たり前
副業でやっている人なら「本業」が終わってから取り組む訳だから、へとへとな状態ですよね。
だから夜や早朝にやるんだから、誰だって眠い、しんどいとか言いたいに決まっています。
元々、今まで「休みの時間」として使っていた時間を、未来より良くなるための「投資時間」として使っていますからね。
だから、お金だけを稼ぎたいなら「投資がいいよ」って言っているのは、お金を出してポチっと押すだけで済むから。
ビジネスって「自分の成長」と「お客さんのハッピー」を願っていくものなので、実際に大変なことなんです。
だから、誰でもかれでもコンサルを受けないのはそういう理由です。(安易にコンサルが主の収入源なのにw)
そして、今
 小田じゅん
小田じゅん人生変えようと努力してる人が激増しています。
インターネットビジネスは
・自宅でできる
・スキマ時間でできる
・パソコン1台でできる
・低予算からできる
・SNSは無料で文字だけで発信できるなど
めちゃくちゃメリットだらけなビジネスではありますが、当然そこにはライバルが「何万人」か存在しています。
これだけの情報化社会において、本気で発信する「量」と「質」を上げなきゃ、誰も見ませんよ。
つまり、取り組む基準値を上げないと、6か月程度の継続力では見てもらえないってことです(繰り返しますが、本気でやっている人が増えてきたからです)
ビジネスって「社会貢献」の要素がありますが、同時に「競争社会」ですからね。
あなたが「疲れた」「だるい」「しんどい」「自信がない」とネガティブな要因を言っている間に
あなたと同じ業界のライバルは「本気で人生変えたい」「ワクワクする!」「何がなんでも成し遂げるぞ!」と燃えている人もいますから。
同じお金を出すのであれば、当然「後者」の人に出したいと思いませんか?
そもそも「自信がない」って言うなら、人の倍は「努力せぇ笑」と言いたい。
なんで今の状態で勝負しようとするんだ。
それは、今の自分は変える気がないと言っているのと同じで、ラクし過ぎだぞ。
それが積み重なっていくと、どんどん情熱もって取り組んでいるライバル達にお客さんが取られますよ。
成長する人は「先生との距離感」がうまい
では、どんな人が短期間で成長するのでしょうか。
これまでの経験から見て、伸びる人は「一定の距離感」を意識的に保っています。
先生を“過剰に頼らず”、かといって“壁を作るわけでもない”。という距離感。
そして
・とりあえずやってみる
・やってみた上で自分の考えを添えた質問を考える
・自分から聞いたアドバイスは素直に受け取る
・成功するためにはビジネス以外の時間を極力とらない
こういった人は「自分の成長を他人に依存しない」というマインドを持っています。
だからこそ、自分の足で立ちながら先生の力も借りることができ、結果的に自走力が育まれていきます。
良い質問ができる人は「相手の立場」が想像できている
成長が早い人にはもう一つ共通点があります。それは「質問力」が高いということです。
たとえば、
×「どうすればいいですか?」
○「〇〇と〇〇で悩んでいるのですが、自分なりには〇〇と考えました。方向性として問題ないでしょうか?」
このように、自分の考えを添えたうえで質問してくる人は、相手の時間や立場に配慮できていると言えます。
これは単なる礼儀ではありません。
“自分で考えた結果”があるからこそ、質問も具体的で深いものになり、得られる答えの質も格段に高まります。
ぶっちゃけこれができない人は、長く生き残ることは難しいでしょう。
「ちょっと壁にぶつかった」時点で、すぐに「自分にはムリだ」「難しい」と行動を止めてしまう、小学生の子よりもひどい名探偵コナンの逆バージョンの状態になります。
「寄り添いすぎ」は毒になる
人は誰しも、つらいとき、苦しいとき、誰かに寄り添ってもらいたくなるものです。
しかし、寄り添いすぎは毒にもなります。
なぜなら「孤独」と「思考」はセットだからです。
自分で考える時間、自分で悩む時間を奪われたら、人は考えなくなってしまいます。
思考停止に陥ります。だから、成長が止まるのです。
“寄り添い=優しさ”ではありません。“突き放し=冷たさ”でもありません。
本当に人を育てるのは、必要なときにだけ差し伸べられる「限定的な支援」です。
成果を出す人ほど「一人で決める覚悟」を持っている
結果を出す人には、一つの明確な共通点があります。
それは「最終決定を人に委ねない」という姿勢です。
助言や意見は求めても、最終的にどう動くかは自分で決める。
その覚悟がある人は、行動のスピードも早く、振り返りの質も高くなります。
責任を自分で引き受ける意識があるからこそ、成長が加速します。この「決断の主体性」が、成果と直結するのです。
支援とは「自立を後押しすること」である
支援とは、依存させることではなく、自立を後押しすることです。
本当に価値ある支援とは、一時的に手を貸すことではなく、「もう大丈夫」と相手が自分で歩き出せる状態をつくることです。
自分で考え、自分で動き、自分で結果を受け止める——そのプロセスを積ませることが、最も本質的な支援です。
まとめ
伴奏型支援のコンサルがキライな最大の理由は、「優しさを装った依存体質の温床」になりやすいからです。
もちろん、すべての伴奏型コンサルが悪いわけではありません。
本当に「相手の成長」を第一に考え、さらに身を削って行動に移されている素晴らしい人もいます。
しかし、相手の機嫌を取りながら“寄り添うフリ”をしつつ、実際は何も育てていないようなコンサルが多すぎます。
成長は「不快」や「違和感」から始まります。
不安、孤独、葛藤、決断——それを自分で乗り越えるプロセスがあってこそ、本物の力になります。
だからこそ、あえて寄り添わず、あえて突き放すことが時として必要だと考えています。
「自分の人生は、自分で変えられる(過剰に人に依存しない)」と気づいた人からしか、本当の意味での成果は生まれないのです。